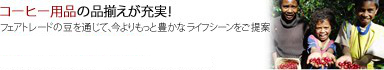焙煎されたコーヒー豆を粉砕するための器具で、主に業務用を指します。一般家庭用は、コーヒーミルと呼びます。
コーヒーメーカー、エスプレッソマシン、フェアトレードコーヒー豆の通販専門サイト
- 現在の商品数:2,579点
- 全品特別価格設定中!
![]()
グラインダー
クレマ
エスプレッソの抽出後、カップに浮かぶ3mm程度の泡状のもので、ムースともいいます。
コーヒーの成分である油脂と湯が乳化したようなコロイド状の泡で、クレマがきちんとできることが、
よいエスプレッソの抽出の証となります。
クロップ
収穫物を意味します。10-11クロップと表示されていた場合は、主に2010年~2011年に掛けて収穫されたコーヒーを
指します。
また、その年に収穫されたコーヒーをニュークロップ、前年に収穫されたコーヒーをパーストクロップと呼びます。
欠点豆
生豆中に混入している不完全豆のことをいいます。
発酵豆、死豆、黒豆、未成熟豆、カビ臭豆などがあります。
焙煎の前後に、ハンドピックしないとコーヒーの味に悪影響を与えます。
コーヒー
コーヒーといって、抽出された液体、粉砕された粉、焙煎された豆、生豆、パーチメント、チェリー、コーヒーの樹等々、
さまざまあり、その範囲が広く意味されます。
コーヒーミル
焙煎されたコーヒー豆を粉砕するための器具です。主に家庭用のものを指す名称で、業務用はグラインダーと呼ぶことが多いです。
コーヒー粉だと、密封して保存しても開封後2、3日で湿気を帯びたり香りが飛んだりしてしまうが、
豆で購入して使うたび毎にコーヒーミルで挽けば、より香り高いコーヒーを愉しむことができます。
コーヒーロースター
コーヒーロースターには、2つの意味で使われます。
その1つは、コーヒーを生豆の状態で仕入れ、焙煎して、卸売りまたは小売りをする業者のことです。
(例:キーコーヒーや上島珈琲 (UCC) のような大規模なものから、街中にある家族経営のものまであります。)
もう1つは、コーヒー豆を焙煎するための機器のことです。コーヒー焙煎器。業務用の大型のものから家庭用までいろいろな種類があります。
コモディティコーヒー
定期市場で取引の対象になっている、一般のコーヒーのことです。
コマーシャルコーヒーともいいます。
これに何らかの付加価値がついたものをプレミアムコーヒーと呼びます。
さらにプレミアムの中でも、特に香味が優れたものをスペシャルティコーヒーといいます。
サイフォン
気圧の差によって湯を移動する仕組みを持った、コーヒーを抽出するための器具です。
1度目の移動には水の蒸気圧による加圧が用いられ、2度目の移動には気体の冷却収縮による減圧が用いられます。
19世紀のヨーロッパで発明されたものであり、日本には大正時代に「コーヒーサイフォン」として紹介され、
その後、「サイフォン」という略称で呼ばれています。
サビ病
雨季に多発するコーヒーの葉の病気です。
葉孔に付着し、菌根をのばして斑点を広げます。
伝染率は高く、かつてセイロン(現スリランカ)やインドネシアのアラビカ種が全滅し、耐病性のあるロブスタ種が
普及するきっかけとなりました。